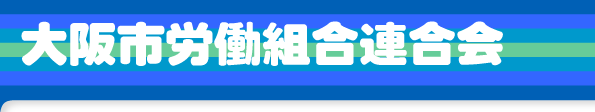「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン」について
2006年6月20日
大阪市労働組合連合会
- 5月26日、大阪市福利厚生制度等改革委員会は第5次報告を公表し、労使関係について「総務局において管理運営事項と交渉事項をわかりやすく整理すべきである」「『ガイドライン』を策定し、周知徹底を図っていく必要がある」として「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン(試案)」を提言しました。これを受けて、総務局においてガイドライン策定が進められてきました。
6月12日、市側・総務局から、策定したガイドラインを早急に所属に通知する旨の情報提供がありました。内容については、「改革委員会の提言を踏まえたものであり文言の変更はできない」「昨年10月の労使協議の整理やその後の取り扱い協議の内容をわかりやすくまとめたもの」「アンケート調査は改革委員会での議論があり削除はできない」等の表明がありました。
これに対して市労連は、(1) 労使交渉等のガイドラインであるならば労使の協議で決めるべきであり、市側が一方的に通告することは問題である、(2) 「昨年10月の労使協議の整理やその後の取り扱い協議の内容をわかりやすくまとめたもの」としているが、一方的に整理を図るものである、(3) また、職員アンケート調査は問題があり反対、これを入れたものをガイドラインとすることは基本的に認めることはできない、との認識を明らかにし、強く指摘しました。
しかし、市側態度の変更には至らず、市側は一方的に策定したガイドラインを近々に所属通知しようとしています。 - 市労連は、以下の基本的認識のもと対応することとします。
(1) 市労連は、労使交渉等のガイドラインについては、労使が十分に協議し合意の上で作成することはやぶさかではありません。
しかし、今回のガイドラインは、労使交渉等のガイドラインであるにもかかわらず、労使協議を一切行わず、「市側の立場」を一方的にまとめたものといわざるを得ません。
福利厚生制度等改革委員会は市側の一機関であり、その立場で提言されたのであり、労働組合の合意のないまま一方的に策定したガイドラインの押し付けを認めることはできません。
市労連は、昨年10月の労使協議の整理やその後の取り扱い協議など、これまでも対応してきましたが、「管理運営事項」にかかわっては各任命権者・担当者の認識によって取り扱い・対応に違いが生じていることも事実です。
地方公共団体の当局と職員団体・労働組合の正常な労使関係については、一般的には「労使対等の原則」「相互不介入の原則」「労使自治の原則」「相互理解の原則」等の原則が守られてこそ成立するものです。
地方公務員法第55条5項においても、交渉にあたっては職員団体と地方公共団体の当局との間において、「議題、時間、場所、その他必要な事項」を取り決めることとなっており、労使の十分な協議・話し合いと合意によってのみ尊重し合えるルール作りが行えるものです。
(2) 福利厚生制度等改革委員会の「管理運営事項」と「交渉事項」に関する見解は、「管理運営事項」とその他の勤務労働条件は明確に区分できるという前提に立っており、「交渉事項」を極めて限定した上で「管理運営事項」に関しては一切交渉してはならないとの立場が基本となっています。
市労連傘下の職員団体・労働組合は、地方公務員法・地方公営企業労働関係法(地公労法)に規定された組合活動を行っていますが、第三次公務員制度審議会答申でも「管理運営事項の処理によって影響を受ける勤務条件は、交渉の対象とする」とされており、地公労法は「管理運営事項」に関しても交渉を禁止してはいません。「管理運営事項」についても、むしろ健全な労使関係の構築、円滑な業務遂行等の観点からは交渉・協議において話し合うことが望ましいとの認識が一般的といえます。
従って、仮に「交渉事項」に該当しない「管理運営事項」にあたるものであっても、市側として、職員団体・労働組合との交渉の中で必要・最適な選択を模索することが肝要といえます。
(3) 本市においては、地方公務員法に基づく交渉に加え、市民サービスを充実する観点から、これまで各種協議会を設置し、労使協議を活性化させてきました。
今回示されたガイドラインは、現行法に基づく極めて限定的な「交渉」にかかるルールだけが明文化されており、労使協議の活性化による行政業務の円滑な遂行と職員の働き甲斐や士気の高揚などをどのように図っていくのかなど、ガイドライン策定の目標が何等明らかにされていません。
市労連は、法令遵守を前提に、現行の交渉制度の維持は当然のこととして、交渉事項に限らず幅広い事項について労使間で意思疎通を図っていくことが、職員の士気や公務能率の向上に資するものと認識するものであり、「労使協議制度」が必要と考えています。
民間においても大企業を中心に広く「労使協議制」が定着しており、多くの経営者が労使の話し合いの場として「労使協議制」を重視するとしています。また、「雇用・人事に関する事項」や「労働時間に関する事項」「職場環境」のみならず、「賃金に関する事項」や「福利厚生」、「経営方針に関する事項」を話し合っている企業も多くあります。日本の企業経営においては、従業員の経営参加・発言を確保する制度として、有効に機能し定着してきています。
(4) 公務の現場でも、いくつかの自治体では、行政諸施策の労使協議の場において、当局側からの単なる情報提供に止まらず、労働組合として職場の意見を吸い上げながら諸施策の評価、実施状況のチェックを行っており、労使協議の活性化、職員の士気向上の観点から、重要な取組みとなっています。
三重県では「労使協働委員会」を設置し、「労使それぞれが自立性を確保しつつ、対等の立場で、情報の共有を前提に、生活者起点のより良い県政の実現をめざして、勤務条件から政策議論に至る幅広い課題について、オープンで建設的な議論を行っていきます」として、県の施策、事業の評価と予算、県庁組織と職員配置、長期計画など、あらゆる課題について労使協議が行われています。
また、「労使協働委員会は政策や事業などを進めるにあたって、職員の声を聞き参考にする」として、原則、業務として勤務時間内に行われており、さらに、職員個々では権限の違いなどもあり、職場や支部を代表した役員と話し合うことによって「対等な議論になるようにする」ことが図られています。
単に、労使関係を「交渉」のみに限ることなく、「信頼」と「対等」そして「対話」を基本とした市政改革のパートナーとしての市政運営が求められていると強く認識するものです。
(5) また、労使関係にかかる「職員アンケート調査のための実施指針」とその「定期的実施」が提言され、ガイドラインに入れられています。
昨年5月の「職員アンケート」の結果を根拠に、なお「不適切な労使関係」があるとされています。さらに、3月の全職員を対象とした「労使関係についてのアンケート調査」の結果は、わずか2.6パーセントの有効回答であり、「労使関係に問題あり・なし」が各82件・79件の半々であるとされていますが、残りの「その他」とされた中には、「十分な労使協議」を求めるものが多くあるにもかかわらず、何ら触れられておらず、極めて意図的なアンケート結果の取り扱いといわざるを得ません。
この間の労使関係アンケートは、「労使関係」としているにもかかわらず、労働組合に一切協議もなく一方的に実施されており、不当労働行為につながりかねないものであり、また、全職員を対象とすることで明らかなように、労働組合と労使関係をはきちがえており、アンケートの目的が明確でなく、アンケートの実施自体が目的化されているといわざるを得ません。
引き続くこのようなアンケートの実施は、職場の混乱を招来しかねず、労使交渉等のガイドラインに「職員アンケート調査」を入れることには問題があり、反対です。
(6) 繰り返しになりますが、今回のガイドラインは、労使協議を一切行わず、「市側の立場」を一方的にまとめたものです。
市労連は、憲法で保障された労働基本権のもと、法令順守は当然として、市側に対し誠実な交渉・協議を求めるものです。
以 上