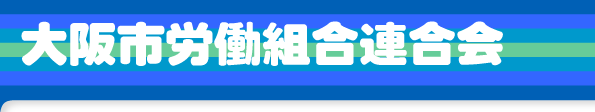「大阪市労働問題法対策会議」の設置について
2005年12月
大阪市労働組合連合会
本市財政状況の悪化については、その大きな要因が第三セクター問題やオリンピック招致など、市当局の行政執行責任にあるにも関わらず、市側はその問題に一切触れることなく、責任を曖昧にしたままの対応を続けており、9月27日に出された「改革マニフェスト」でもそれらの問題にはほとんど触れておらず、財政危機の責任を「厚遇問題」等の労働組合批判を利用し労働組合・職員に転嫁して、責任回避をはかろうとしている。
財政危機の中で、昨年末以来、一連のマスコミ報道から発した大阪市の今日的状況は、労働組合・労働組合活動に対する市民の方々からの批判に拡大し、市労連をはじめ各労働組合は、これまでの経過にこだわらず「改めるべきは改める」との姿勢で対応しているが、市側は、引き続き「労働組合=悪のイメージ」を利用して、労働組合・職員に責任転嫁をはかろうとしてきている。そして、十分な労使協議が行われないまま「福利厚生制度」等の一方的な見直しが行なわれてきた。
さらに、「互助組合連合会給付金」をめぐっては、市労連・元役員に対しても返還請求裁判が提訴される状況となっている。
また、労働組合活動については、10月から「ながら条例」の見直し等が行なわれたにも関わらず、マニフェスト等では「労働組合との関係調査」、「労使協議の限定・ルール化、ルールに反すれば処分」、「労使協議とは別個の意見交換会の開催」等、労働関係法、労使関係を全く無視して実施されようとしている。
まさに、「労使協議」「労使交渉・合意」とは何かなど、法的な議論と対策が必要な状況となっている。
これらの動きは、小泉改革の名の下、官公労潰し・公務員制度改悪にも利用されている。
この間、連合大阪法曹団、大阪労働者弁護団、自治労府本部・各単組顧問弁護士の協力を得て、「対策会議」の設置にむけてとりくみを行ってきた。
これらのとりくみを踏まえて、「大阪市労働問題法対策会議」(以降「対策会議」)を設置し、一連の問題に対して法的対応を含めたとりくみを行うこととする。
以上